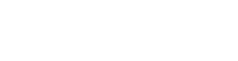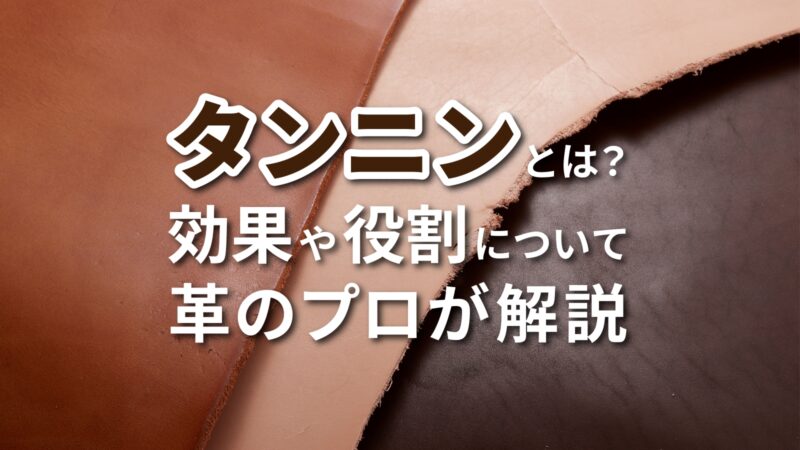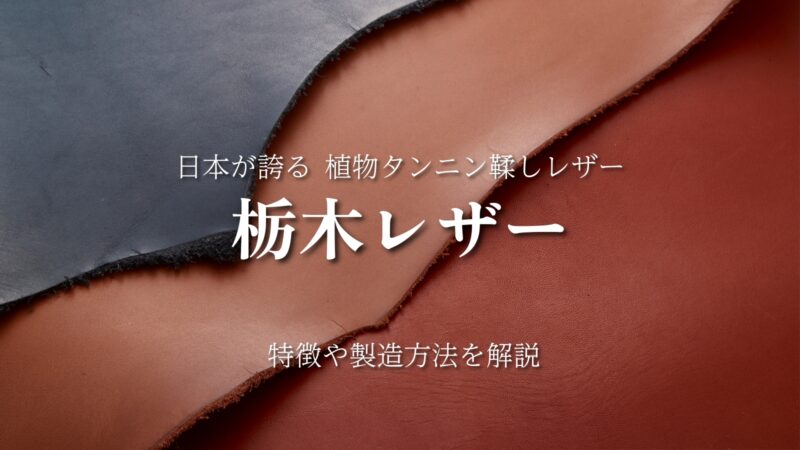染料と顔料の違いとは?|仕上げで変わる革の表情

革製品を手掛けるうえで欠かせない工程の一つに「染色」があります。
同じ革でも、染め方は仕上げ方法によって見た目も触り心地もまったく異なる印象になります。
その中でも代表する2つの染色である「染料仕上げ」「顔料仕上げ」があります。
どちらも革に色を付けるための工程ですが、その性質や仕上がりは、大きく異なります。
本記事では、その「染料仕上げ」「顔料仕上げ」2つの染色方法の違いを分かりやすく解説。
特徴や使われ方についてもご紹介いたします。
染料と顔料の違いとは?
それぞれの基本的な特性についてご紹介。
染料は、革の繊維に浸透して染まるタイプの色素です。
水に溶けやすい性質を持ち、革の内部まで色が入り込むため、ナチュラルな発色に仕上がります。
一方で顔料は、革の表面に塗料を塗ることで、着色します。革の表面に膜を作ることで、しっかりと色を定着させます。
発色が均一で色ムラができにくく、色落ちや色移りがしにくい特徴を持っています。

つまり、
染料=革の繊維に染色させる
顔料=革の表面に色の膜を作る
という違いが一番大きなポイントです。
染料仕上げの特徴と魅力
染料仕上げの魅力は、革本来の質感をそのまま活かせる点にあります。
革の表面を覆わないため、革の表情や自然な色ムラ、経年変化がそのまま現れます。
その味わいこそが革好きにとって大きな魅力といえます。
染料仕上げの革は、使い込むほどに色の深みやツヤが増していく経年変化(エイジング)を楽しむことが出来ます。
ナチュラルな風合いや色合いは、顔料では再現しにくいものです。
ナチュラルな反面、デリケートな一面もあります。
水や摩擦に弱く、傷や汚れが目立ちやすいデメリットもあります。
また、美しいエイジングには定期的なメンテナンスも欠かせません。
ただ、その手間もまた、育つ素材としての魅力を高める要素でもあるといえます。
顔料仕上げの特徴と魅力
顔料仕上げの革は、革の表面を顔料の膜で覆うため、発色が均一で美しく、染料仕上げの革と比べて水や汚れに強い特性を持っています。
メンテナンスも容易で、扱いやすいメリットもあります。
一方で、表面を覆うため革本来の質感や風合いは少し失われやすく、風合いという点では染料仕上げに劣る場合もあります。
そのため経年変化も少なく、「長年使いこむことで味が出る」というよりは、最初の美しさをキープするタイプの仕上げです。
染料と顔料、どっちがいい?
結論から言うと、どちらが優れているというよりは、目的や用途によって選択が変わるイメージになります。
簡単に例えると、
革本来の質感やエイジングを楽しみたい場合は:染料仕上げ
均一な色味・強度を重視する場合は:顔料仕上げ
といった風に使うシーンや求める仕上がり使い分けるのが一般的です。
フジリュウでも、製品の用途やお客様のご要望に応じて、染料仕上げ・顔料仕上げいずれの革の選定も対応可能です。
OEM製作の際には、「どんな場面で使われる製品なのか」「どんな質感を出したいのか」などヒアリングし、ご要望に沿った革の使用を提案いたします。
染料仕上げと顔料仕上げの見分け方
染料仕上げの革と顔料仕上げの革の見分け方は、質感や色の付き方などによって区別することが出来ます。
染料仕上げの見分け方
・色むらがある場合がある。
・色に透明感があり表面の傷やシワなどが見えている。
顔料仕上げの見分け方
・表面が均一な色で、塗膜が張られているような印象。革のシミなどが見えない。
・水に濡らしてもはじく場合があります。
まとめ
革の染料仕上げと顔料仕上げの違いは、単なる技術的な差ではなく、製品の個性を左右する大切な要素の一つです。
革本来のナチュラルさや表情を楽しむなら染料仕上げ、発色の安定性と機能性を重視するなら顔料仕上げがオススメ。
フジリュウでは、これらの仕上げ方法で造られた革を製品コンセプトに合わせて選び抜き、お客様の理想の革製品をカタチにしていきます。
ぜひ次に革製品を手に取るときは、その色と質感の奥にある仕上げの違いについても注目してみてください。