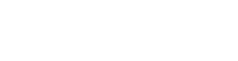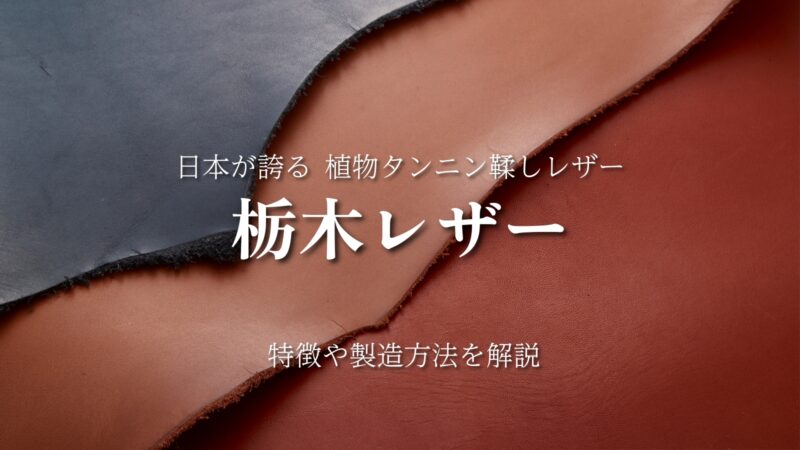タンニンとは?|効果や役割について解説
革製品を語るうえで欠かせないキーワードの一つが「タンニン鞣し」。
その「タンニン鞣しのタンニンってなに?」と疑問に思ったことはありませんか?
タンニンは、ワインやお茶の渋み成分としても知られていますが、実は革づくりにおいて非常に重要な役割を果たしています。
今回は、そんなタンニンの基本的な性質から、革づくりにおける役割、そしてタンニンなめし革の魅力について詳しく解説します。
タンニンとは?
タンニンは植物の樹皮、果実、葉、根などに含まれるポリフェノールの一種で、一般的には「渋み成分」として知られています。
「タンニン(tannin)」という言葉は、英語の「tan(なめす)」という単語に由来しており、もともと皮をなめす(革にする)ために使われる成分という意味を持っています。
自然界では、植物が外敵から身を守るために生成する成分でもあり、抗菌・防腐・収れん作用を持つのが特徴です。
その性質が革づくりにおいても活かされ、動物の皮を腐らせずに長持ちさせる「革」へと変えることができます。
タンニンの役割
動物の皮は、そのままでは時間の経過とともに腐敗してしまいます。
そこで登場するのが「なめし(鞣し)」という工程です。
この工程では、皮に含まれるコラーゲン繊維にタンニンを結合させることで、耐久性・柔軟性・防腐性を高め、長期的に使用できる「革」へと変化させます。
タンニンを使ったなめし方法は「タンニンなめし」と呼ばれ、昔ながらの伝統的な製法として世界中で受け継がれています。
イタリアのトスカーナ地方や日本の姫路・栃木などでも、このタンニンなめしを得意とするタンナー(革の製造工場)が多く存在します。
何の植物のタンニンを使っている?
ミモザ

ミモザの樹皮や葉にはタンニンが含まれており、強い収れん作用(革を引き締める性質)を起こし、革内部の密度を高め、やわらかく、しなやかな風合いの革を作るのに適しています。
チェストナット
ヨーロッパで古くから利用されている植物タンニンです。
ミモザなどより収斂性が低いため、じっくりと時間をかけて革の内部までしみこませます。
ミモザなど使用して鞣した革と比べ、空気や紫外線との反応がしにくい性質を持っているため、経年変化が緩やかになります。
オーク

どんぐりの実がなることで知られるオ-ク。
ヨーロッパで古くから使われてきた伝統的なタンニン源です。
オークバーク(樹皮)から抽出されたタンニンは、革に独特の深い色味と強度を与えます。
特にイギリスの老舗タンナーでは、靴底用の「ソールレザー」のなめしに今でもオークを使用しており、長期熟成型のなめしにも向いています。
タンニンの種類と効果
タンニンは主に「加水分解性タンニン」と「凝集性タンニン」の二種類に分類されます。
加水分解性タンニン
加水分解性タンニンは、水に分解される性質をもつタンニンです。
縮合性のタンニンに比べ収れん性が高くないため、時間をかけて皮にしみこませることで鞣すことが出来ます。
しなやかで発色のいい仕上がりになります。
縮合性タンニン
縮合性タンニンは、水に分解されにくく、構造的に安定しているタンニンです。
収れん性が強く、繊維が詰まっており、ハリとコシのある仕上がりになります。
縮合性タンニンでなめされた革は大きな経年変化をすることも特徴的です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
タンニンは、単なる植物成分ではなく、皮を革へと変えるなめしにおいて重要な存在です。
自然由来の成分でありながら、長い年月にわたり人々の暮らしを支えてきた伝統技術の根幹でもあります。
フジリュウでも、こうしたタンニンなめし革を使用した製品づくりやOEM製作を数多く手掛けています。自然の力を活かした素材の美しさを大切にしながら、お客様のご要望に合わせた高品質な革製品をご提案しています。
「経年変化を楽しみたい」「自然素材のぬくもりを感じたい」
そんな方には、ぜひタンニンなめし革を手に取ってみてはいかがでしょうか。