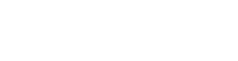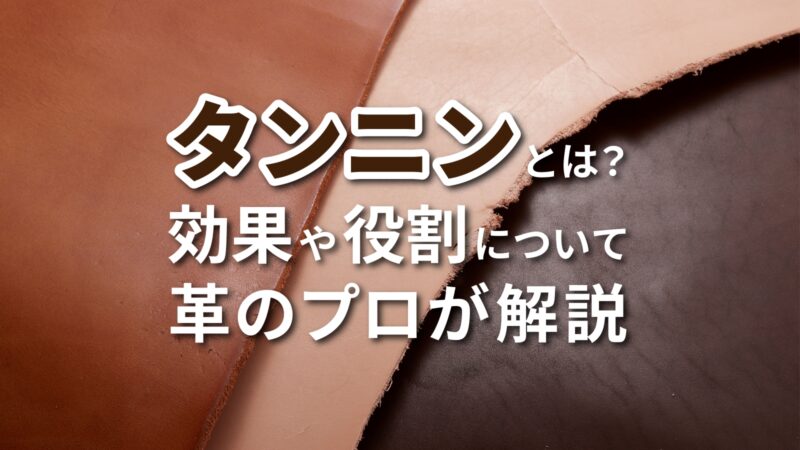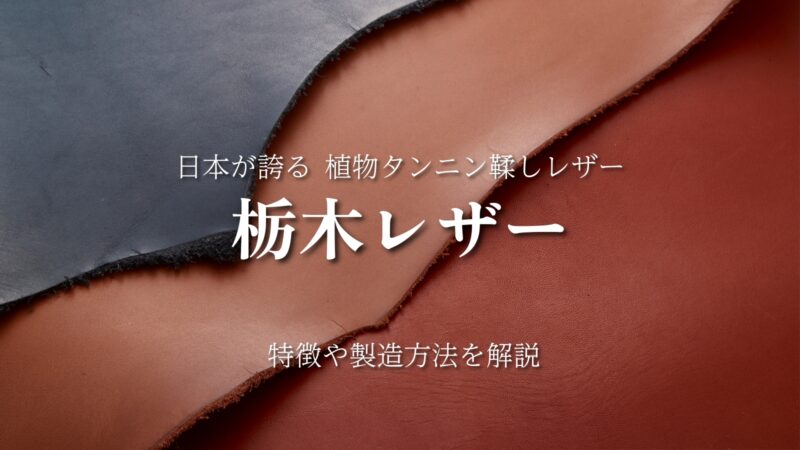コンビ鞣しとは?|タンニン×クロムのハイブリッドレザーについて解説
革製品を選ぶとき、注目するポイントの一つとして「タンニン鞣し」や「クロム鞣し」といった鞣しの方法があります。
これらは動物の皮を製品などに使用される素材へと加工する「鞣し」という方法の一つで、その鞣し方によって革の特性が異なります。
そんなタンニン鞣しやクロム鞣し、それぞれの特性を併せ持つ「コンビ鞣し」という鞣しの方法があるのをご存じでしょうか?
本記事では「コンビ鞣し」の特性や製造方法などについて、有名な「タンニン鞣し」や「クロム鞣し」との違いを交えて徹底解説。
革製品選びの参考にしてみてください。
鞣しとは?
まず、「鞣し(なめし)」とは、動物の皮(原皮)を製品などに使える素材、「革」に変えるための加工のことを指します。
加工されていない皮のままだと、腐敗や硬化してしまうため、それらを防ぎつつ柔軟性や耐久性を持たせるために、植物のタンニン(渋)や薬品などを使用して処理する必要があります。
鞣しの方法は様々ありますが、主に「タンニン鞣し」と「クロム鞣し」が有名です。
タンニン鞣し
植物のタンニン(渋)を使用して皮を鞣す方法。加工に時間と手間がかかりますが、革本来のナチュラルな仕上がりと、使い込むほどに色に深みが増したり艶が出てくるなど、経年変化を楽しむことができる特徴を持っています。
クロム鞣し
クロム鞣しとは、塩基性硫酸クロム薬品という化学薬品を使用して革を鞣し製法の一種です。短時間で大量生産できる製法の為、現在では革製品の多くに使用されているポピュラーな革です。タンニン鞣しの革とは違い、派手な経年変化は起こりませんが、柔軟性・耐久性共に優れています。
その他、鞣しの特徴や工程などについてコチラのコラムで詳細に解説しています。
コンビ鞣しとは?|タンニンとクロムのハイブリットレザーについて
「コンビ鞣し(コンビネーション鞣し)」とは、先ほど解説した「タンニンなめし」と「クロムなめし」の両方の特性を活かしたハイブリッドなめし技術のことを指します。基本的には、先にクロムでなめしてから、植物タンニンで再加工するという2段階の工程で作られます。
この製法により、タンニンなめしの風合いと経年変化、クロムなめしの柔軟性と耐久性の両立が可能になります。
コンビ鞣し革のメリット
コンビ鞣しレザーの
1. 絶妙な硬さと柔らかさのバランス
クロムなめしの柔らかさとタンニンなめしのコシを併せ持つため、程よい硬さとしなやかさがあります。財布や鞄、靴など、幅広い製品に適しています。
2. エイジングも楽しめる
タンニン成分を含んでいるため、ある程度の経年変化を楽しむことができます。使うほどに味わいが出るのが魅力です。
3. 発色と色持ちがよい
クロムなめしの要素を含むため、染料や顔料のノリが良く、色鮮やかな表現が可能。かつ色落ちしにくいという特長があります。
コンビ鞣しの流れ
原皮にクロムを使って「クロム鞣し」を施し、革を柔軟かつ耐久性のある状態にします。次に、水洗いや脱クロ処理を行い、クロム成分を一部除去した上で、植物タンニンを用いた「タンニン鞣し」を加えます。これにより、タンニン特有の経年変化や質感が革に加わり、しなやかで扱いやすい仕上がりとなります。
コンビ鞣しに重要な脱クロ処理
クロムなめしに使用される「塩基性硫酸クロム」は、非常に強力ななめし剤であり、短時間で革の繊維を安定させる効果があります。しかし、このクロム成分はそのままではタンニンなめし剤との反応に影響を与える場合があります。つまり、クロムを含んだままタンニンなめしを施してしまうと、タンニン剤が繊維にうまく浸透しなかったり、発色にムラが出たりするリスクがあるのです。
そのため、クロムなめしを施した後に、革の表面からクロムをいったん洗い流す「脱クロ処理」が必要になります。この工程により、次に行うタンニンなめしの効果が発揮されやすくなり、最終的に高品質なコンビ鞣し革を生み出すことが可能になります。
まとめ
コンビ鞣し革は、「経年変化を楽しみたいけど扱いやすさも欲しい」「高級感がありながら日常使いできる革がいい」というニーズにぴったりな素材です。
タンニンとクロム、それぞれの長所を活かしたハイブリッドな製法により、美しさ・耐久性・実用性を高いレベルで実現しているのがコンビ鞣しの魅力。革製品を選ぶ際は、ぜひその「なめし製法」にも注目してみてください。